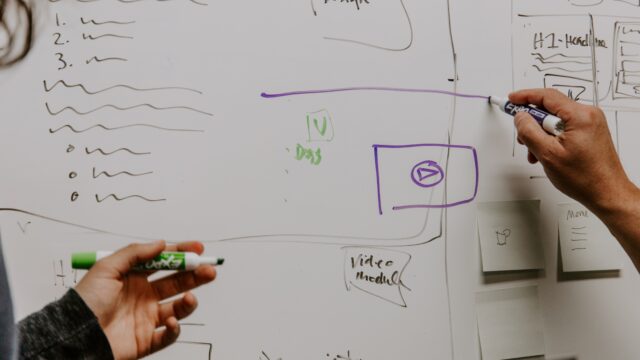※)2024年1月の著作権法改正に関してアップデートしました(2024/12)
オープンソース講座(2)・著作権法におけるプログラムの位置づけ
著作権におけるプログラムの位置づけ

あらためて日本の著作権法 全124条の構成を再掲します。
・総則(1条~9条の2)
・著作者の権利(10条~78条の2)
・出版権(79条~88条)
・著作隣接権(89条~104条)
・私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)
・紛争処理(105条~111条)
・権利侵害(112条~118条)
・罰則(119条~124条)
全体の体系は一見すっきりしているように見えますが、残念ながら著作権法はもともとコンピュータプログラムの「他者に勝手に使わせない権利」を保護するために作成されたものではありません。
それまでの著作物とは性質もかなり異なり、しかも現時点で一番最後に追加されたものなので関係する条文に無理やり(というといいすぎですが)追加されているように見えてしまいます。
コンピュータプログラムの条文解説

著作権法の中でコンピュータプログラムがいかにまま子扱いされているか(笑)を、条文レベルで解説していきましょう。
但し、煩雑になるので条文全体を示すのではなく、各条文の中でコンピュータプログラムがどのように組み込まれているのかを(解説)の部分で解説していきます。
但し、これはあくまで個人的な解釈なので、より正確に知りたい方は直接条文をお読みになることをお勧めします。
(条文はこちらから)
(定義)
・第二条
(解説)
ここでは以降の条文で使用する用語を定義している。
(十の二)にプログラム、(十の三)にデータベースが定義されている。
(著作物の例示)
・第十条
(解説)
第1項の著作物の例示の中の最後に第9号として「プログラムの著作物」が追加されており、同条第3項に以下の3つは保護の対象外としている。
(一号)プログラム言語
(二号)通信などのプロトコル
(三号)アルゴリズム(卑近な例として、ソーティング、リカーシブ、ハッシュ関数等)
(職務上作成する著作物の著作者)
・第十五条 第1項、第2項
(解説)
業務で作成するプログラムの著作権者は契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り法人に帰属する、としている。
(同一性保持権)
・第二十条
(解説)
第一項で著作者は同一性を保持する権利を有するが、例外として第二項に挙げる4つのケースがあるとした上で、その3つ目(第三号)に「特定の電子計算機で利用するためのプログラムの改変」は合法としている。
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
・第四十七条
(解説)
自分のパソコンで利用するための複製が認められている。
(第一発行年月日などの登録)
・第七十六条
(解説)
「第七十六条の二」として創作後6か月以内ならばプログラムの著作者は創作年月日の登録ができる、としている。
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
・第七十八条の二
(解説)
原文を以下にそのまま引用するが、ここでいう「別の法律」というのは商標権のことと推測するが詳細は不明だ。
「プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。」
(侵害とみなす行為)
・第百十三条
(解説)
第二項を要約すると、以下のとおりである。
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物だと知りながら業務上電子計算機で使用する行為は著作権侵害とみなす。
(罰則)
・第八章
(解説)
「第百二十条二」として以下に該当する者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す、としている
この条文は第四号までありあいまいで冗長な条文が続くが、要約すると所謂DRM違反者や人格権、隣接権などの財産権を侵害したもの等が挙げられている。
以上が、日本の著作権法本文の中でプログラムについて規定されている全てですが、いかがでしょうか?
このような状況の中で登場したのが次に説明する法律で、これで全てが解決されるわけではありませんが、著作権という一般法に対して、コンピュータプログラムを保護するための特別法があるということはそれだけでも前進ではないでしょうか。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(2021/6/1)
2021年6月1日に施行された第四条により、著作権者はコピーされたプログラムが文化庁に登録しているものと同一であることを文化庁長官に請求できるようになりました。
これにより、著作権侵害の訴訟がより迅速に解決される可能性が高まりました。
2024年1月の著作権法改正
2024年1月の著作権法改正について、プログラムに関わる部分を中心にわかりやすく説明します。
損害賠償額の算定方法の見直し
この改正は、海賊版ソフトウェアの被害に対してより効果的な対策を取れるようにするものです。
例えば、人気ゲームソフトの開発会社「ゲームクリエイト社」を想像してみましょう。彼らが開発した大ヒットゲーム「スーパーモンスターバトル」が海賊版として不正にコピーされ、インターネット上で広まってしまったとします。
改正前:
ゲームクリエイト社が請求できる損害賠償額は、自社の販売能力に基づいて計算されていました。例えば、1年間に100万本しか製造・販売できない能力しかなかった場合、それ以上の被害額を請求するのは難しかったのです。
改正後:
ゲームクリエイト社の製造・販売能力を超えた分についても、ライセンス料相当額として損害賠償を請求できるようになりました。つまり、100万本を超えて不正コピーされた分についても、1本あたりのライセンス料を基準に損害賠償を求められるようになったのです。これにより、海賊版ソフトウェアの被害に対して、より公平で適切な賠償を受けられる可能性が高まりました。
新たな裁定制度の創設
この改正は、著作権者の連絡先がわからない場合でも、一定の条件下でプログラムを利用できるようにするものです。
例えば、「古いゲーム愛好家のタロウさん」を想像してみましょう。タロウさんは、20年前に発売された懐かしのゲーム「レトロクエスト」を現代の機器で遊べるようにリメイクしたいと考えています。しかし、開発会社は既に解散しており、著作権者に連絡が取れない状況です。
改正前:
タロウさんは著作権者の許可なしにゲームをリメイクすることができず、プロジェクトを諦めざるを得ませんでした。
改正後:
新しい裁定制度を利用することで、タロウさんは一定の条件を満たせば「レトロクエスト」をリメイクできる可能性が出てきました。具体的には、文化庁に申請を行い、使用料に相当する金額を供託することで、一定期間ゲームを利用できるようになります。この制度により、古いソフトウェアの再利用や、過去の優れたプログラムの現代での活用がしやすくなることが期待されます。
これらの改正により、プログラムの著作権保護がより強化され、同時に利用の円滑化も図られることになりました。ソフトウェア開発者と利用者の双方にとって、より公平でバランスの取れた環境が整備されつつあるといえるでしょう
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」について補足
1,本法律は特別法なので、一般法である著作権法に優先して適用される。
2,参考までにの第四条を引用しておく。
(プログラム登録に関する証明の請求)
第四条 プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。
2 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
まとめ