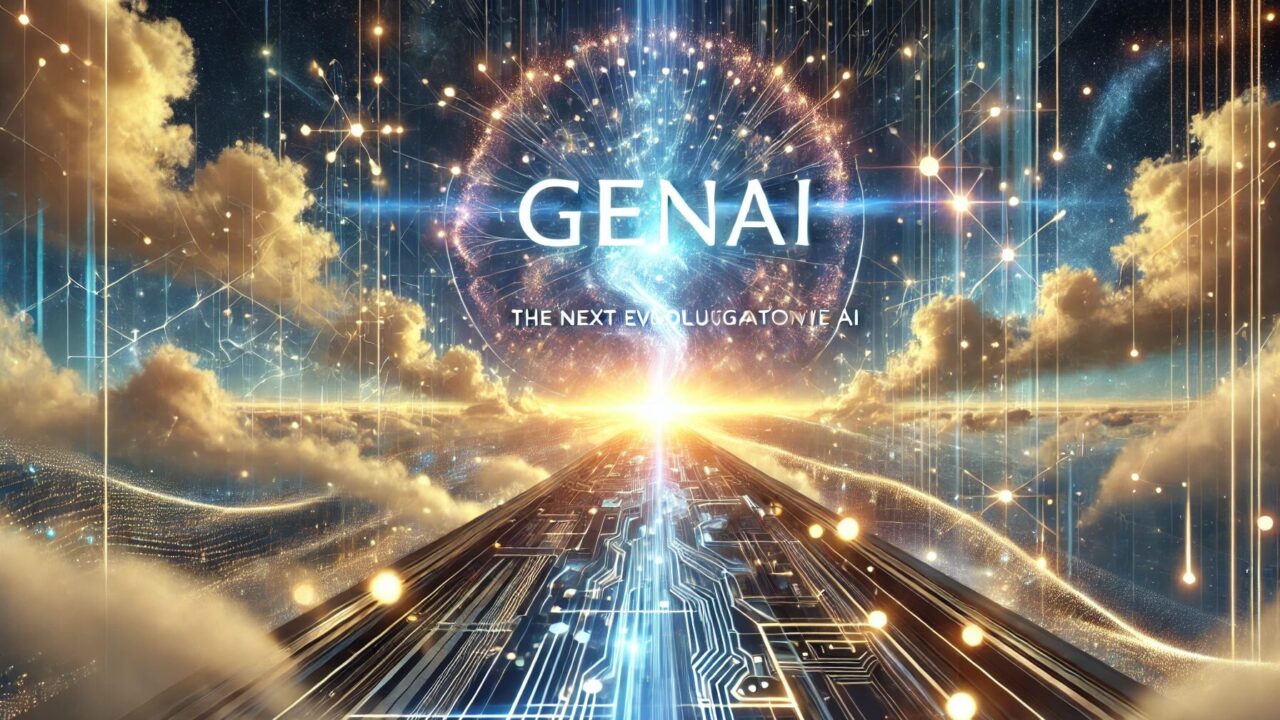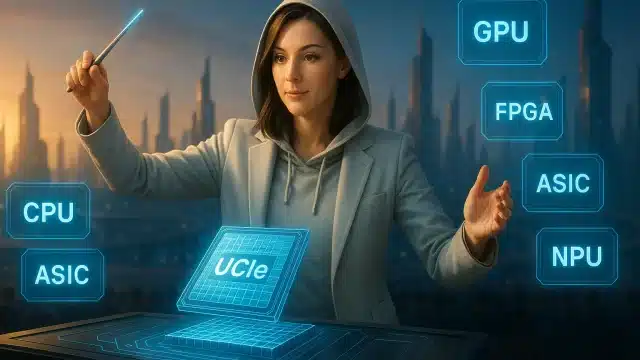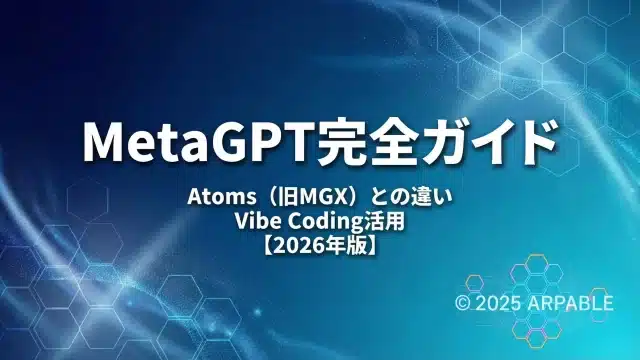DeepSeekとSakana AIに見る生成AIの新たな潮流
この記事を読むと 生成AIの最新コスト構造と技術トレンドが分かり、自社のAI戦略を見直すヒントを得られる ようになります。
この記事の信頼性の源泉
AIの仕組みをやさしく解説します。筆者は長年ハード・ソフト、クラウド、人工知能を手がけるエンジニアで、2015年からディープラーニングや生成AI・LLMを継続的に研究。現場経験を生かし、最新情報を噛み砕いてお届けします。
生成AI(ジェネレーティブAI)の進化は、私たちの生活やビジネスの風景を劇的に変え続けています。2025年に入り、AI技術は新たな段階へと突入し、その挑戦はますます多様化しています。
本記事では、生成AIの新たな潮流として注目される3つの主要なポイントを、具体的な例やたとえ話を交えながら解説します。特に、新興企業であるDeepSeekとSakana AIの技術革新に焦点を当て、これらの企業がどのようにしてAI業界に新風を巻き起こしているのかを探ります。
1. 論点が「学習」から「推論」にシフト
◆ セクション要約:AI開発の焦点が、モデルを育てる「学習」から、賢く使う「推論」の効率化へ移行。その背景と新技術を解説します。
従来のLLM開発と新たな課題
これまで、大規模言語モデル(LLM)の開発は主にモデルの学習(トレーニング)に焦点が当てられてきました。しかし近年、AIモデルの開発において、学習フェーズだけでなく推論フェーズの重要性が急速に高まっています。推論とは、学習済みモデルを用いて実際のタスクを実行するプロセスであり、その効率性やコストは、AIの実運用における経済合理性を左右する大きな要素です。
この背景には、学習に対する投資対効果の低下が挙げられます。学習コストの増大に対して得られる性能向上の幅が次第に小さくなり、いわゆる「スケーリング則の限界」に直面しつつあります。また、主要な公開データの多くが既に学習に使用されており、追加で大規模な高品質データを調達しにくい状況が生まれつつあるという課題も顕在化しています。
こうした状況の中で、「既存の知識をいかに効率的に活用し、より精度の高い推論を行うか」という視点が重要になっています。特に、モデルに多段階思考を促す高度なメタプロンプト技法(俗称“パワハラプロンプト”)や、AI自身が思考を繰り返して結論を洗練させる手法は、AIが自律的に問題を解決し、より精緻な結果を導き出すための手段として注目されています。
かみ砕きポイント:高性能なシェフとキッチンの効率化

AIの学習を「シェフの技術習得」、推論を「料理の提供」に例えます。最高のシェフもキッチンの段取りが悪ければ、美味しい料理を素早く出せません。同様に、AIも学習した知識をいかに効率よく引き出すか(=推論の効率化)が、ビジネスで価値を生む鍵となるのです。
DeepSeekとSakana AIのアプローチ
DeepSeekは、推論の効率化に注力しています。特に、同社の`DeepSeek-V2`モデルは、236B(2360億)パラメータのうち、実際に計算で利用するアクティブなパラメータを21B(210億)に抑える独自のMoEアーキテクチャにより、推論コストを大幅に削減しています。
Sakana AIも同様に、推論の革新に取り組んでいます。同社のTransformer²は、推論時にモデルの重みを自己適応的に再構成する革新的なアーキテクチャです。Sakana AIは公式ブログにて、社内ベンチマーク比で「最大4倍高速」と報告していますが、公開論文における定量的な値は限定的であり、今後の外部検証が待たれます。
Key Takeaways(持ち帰りポイント)
- AI開発の主戦場は、コストのかかる「学習」から、運用効率が問われる「推論」へとシフトしています。
- 学習データの限界と投資対効果の低下が、この「推論重視」の流れを加速させています。
- 高度なプロンプト技術や自己修正能力は、AIの推論能力を最大限に引き出すための重要な鍵です。
- DeepSeekとSakana AIは、この推論効率化の潮流をリードする代表的な企業です。
2. 大規模至上主義から「専門家(コンパクトモデル)の連携」へ
◆ セクション要約:巨大な万能AIから、特定の仕事に特化した「専門家AI」を連携させる時代へ。MoE技術を中心にそのメリットを解説します。
大規模至上主義の限界と新たなアプローチ
従来、LLMの発展は「大規模化」が中心テーマでした。しかしこの方法には、莫大な計算コストと環境負荷、そして単一モデルでは多様なタスクに対する専門性を持たせにくいという限界があります。これに対抗する形で、よりコンパクトで専門性の高いモデルを複数連携させるアプローチ、MoE(Mixture-of-Experts)が注目されています。
かみ砕きポイント:総合病院と専門クリニック
巨大な単一AIを「何でも診る巨大な総合病院」とすると、MoEは「心臓外科、脳神経外科といった高度な専門クリニックのネットワーク」です。患者(タスク)の症状に応じて最適な専門医(専門モデル)が対応するため、より高度で効率的な治療(処理)が可能になります。
DeepSeekとSakana AIの取り組み
DeepSeekの`DeepSeek-V2`が採用するMoEは、このアプローチの代表例です。タスクに応じてトークンごとに少数の専門家(エキスパート)モデルのみを動的に活性化させることで、計算量を理論上大幅に削減しています。
Sakana AIのTransformer²も、複数の専門知識を持つモデルを効率的に融合・再構成する思想に基づいています。これにより、異なるタスクに対して専門的な能力を柔軟に発揮し、全体のパフォーマンスを向上させます。
かみ砕きポイント:レゴブロックで最強のロボットを作る
Sakana AIの技術は、いろいろな得意分野を持つAIの「部品(既存モデル)」を、レゴブロックのように巧みに組み合わせる仕組みです。例えば、すでにあるロボットの腕や脚(AIの良い部分)だけを選んでパパッと合体させ、新しい「最強のロボット(高性能AI)」を作ります。ゼロから全部作るより、ずっと速く、低コストで高性能なAIが完成するのです。
Key Takeaways(持ち帰りポイント)
- 巨大な単一モデルの開発は、コストと専門性の面で限界に直面しています。
- これからの主流は、複数の「専門家モデル」を連携させてタスクを処理するMoEアーキテクチャです。
- MoEは、必要な専門家だけを動的に呼び出すため、計算リソースを大幅に節約できます。
- DeepSeekの`DeepSeek-V2`は、このMoEアプローチを体現する先進的なモデルです。
3. GPUパワーセーブモードへの挑戦
◆ セクション要約:AIの進化を支えるGPU。その爆発的な需要と消費電力が新たな課題に。持続可能なAIのための省エネ技術に迫ります。
GPU需要の高騰と持続可能性という課題
AI技術の発展に伴い、GPU(Graphics Processing Unit)の需要が急増し、そのコストと消費電力が大きな課題となっています。これは企業のAI導入の障壁となるだけでなく、環境への影響も無視できません。持続可能なAI開発のため、GPUの効率的な利用が急務となっています。
かみ砕きポイント:GPU版「ジェボンズのパラドックス」

「ジェボンズのパラドックス」とは、技術進歩でエネルギー効率が向上すると、利用が促進され、逆に総エネルギー消費が増加する現象です。GPUの効率が上がると、AIの利用がさらに拡大し、結果として世界の総GPU消費電力が増加してしまう可能性を秘めているのです。
DeepSeekとSakana AIのソリューション
DeepSeekのMoEアーキテクチャは、必要なエキスパートモデルのみを動的に呼び出すことで、GPUリソースの消費を最小限に抑えます。これにより、総合的なコスト削減と省電力化を実現しています。
Sakana AIは、SVF(Singular Value Fine-tuning)など、モデルの重みを効率的に調整するPEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning)手法を活用し、少ない計算リソースでモデルの性能を引き出すアプローチを探求しています。
Key Takeaways(持ち帰りポイント)
- AIの発展は、GPUの消費電力とコストという大きな壁に直面しています。
- 効率化が逆に総消費量を増やす「ジェボンズのパラドックス」という視点も重要です。
- DeepSeekのMoEやSakana AIのPEFTは、GPUを賢く使うための具体的な解決策となります。
4. 共通点と市場への影響
◆ セクション要約:2023年設立の新興企業、DeepSeekとSakana AI。両社の共通戦略と、AI市場の価格破壊や技術革新への影響を分析します。
DeepSeekとSakana AIには、いくつかの共通点が見られます。これらが市場に与えるインパクトは計り知れません。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 新興スタートアップ | 両社とも2023年設立ながら、急速に業界内で注目を集めている。 |
| 効率性とコスト削減 | 計算コストと運用コストを劇的に削減する技術を核としている。 |
| 革新的アプローチ | MoEや進化的モデル融合など、従来の大規模化とは異なるアプローチを採る。 |
| GAFA(M)への挑戦 | 大手AI企業に対抗し、市場に技術革新と価格競争を促進している。 |
彼らの登場により、これまで大手企業に限定されがちだった高性能AIの利用が、中小企業やスタートアップにも広がりつつあります。これらの高効率モデルの登場により、大手クラウドAIサービスのAPI価格競争が激化しています。例えば、DeepSeekは2025年2月にオフピーク料金を最大75%値下げすると発表し、主要クラウド3社も2024年から25年にかけてAPI料金を30-50%引き下げており、市場全体に大きなインパクトを与えています。
Key Takeaways(持ち帰りポイント)
- DeepSeekとSakana AIは「効率化」と「コスト削減」を武器にAI市場へ参入したゲームチェンジャーです。
- 両社の戦略は、GAFA(M)が支配してきた市場に、健全な価格競争と技術革新をもたらしています。
- 結果として、高性能AIがより多くの企業にとって利用しやすくなる「AIの民主化」が進んでいます。
まとめ
2025年のAI業界は、巨大さや力任せの「学習」から、賢さや効率を重視する「推論」へと舵を切っています。DeepSeekが示すMoEアーキテクチャや、Sakana AIが探求する進化的モデル融合は、低コストで高性能なAIを誰もが使えるようにする「AIの民主化」を加速させる鍵です。この大きな潮流を理解することは、あらゆるビジネスの未来戦略を描く上で、今や不可欠な要素と言えるでしょう。
専門用語まとめ
- 生成AI (Generative AI)
- テキスト、画像、音声などの新しいコンテンツを自ら作り出すAI。本記事で扱うLLMは、テキスト生成AIの一種です。
- LLM (Large Language Model)
- 大規模言語モデル。膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり理解したりする能力を持つAIモデル。
- 推論 (Inference)
- 学習済みのAIモデルを使って、実際にタスク(質問への回答、文章の要約など)を実行するプロセス。運用コストに直結します。
- MoE (Mixture-of-Experts)
- 専門家混合。複数の小規模な専門家モデル(エキスパート)を組み合わせ、タスクに応じて必要な専門家だけを呼び出す効率的なAIアーキテクチャ。
- PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning)
- パラメータ効率の良いファインチューニング。モデル全体を再学習するのではなく、ごく一部のパラメータのみを調整することで、低コストでAIを特定タスクに特化させる技術群。
よくある質問(FAQ)
Q1. なぜ今、「推論」の効率が重要視されているのですか?
A1. 主に2つの理由があります。第一に、AIモデルの学習コストが非常に高くなり、投資対効果が見えにくくなってきたこと。第二に、インターネット上の高品質な学習データが枯渇しつつあり、モデルを巨大化させる従来の方法が限界に近づいているためです。そのため、既存の知識をいかに賢く低コストで使うか(=推論の効率)が、ビジネスの競争力に直結するようになりました。
Q2. DeepSeekやSakana AIの技術は、中小企業でも利用できますか?
A2. はい、むしろ中小企業やスタートアップにとって大きなチャンスです。彼らの技術は、高性能AIの運用コストを劇的に下げることを目的としています。これにより、これまで資金力や計算リソースの面で大手企業にしか手が出せなかった高性能AIを、より多くの企業が安価に利用できる道が開かれます。
Q3. これから巨大なAIモデルは、もう不要になるのでしょうか?
A3. いいえ、基盤となる巨大モデルが不要になるわけではありません。最先端の研究開発では、今後も基礎体力となる巨大モデル(基盤モデル)の開発は続くでしょう。ただし、多くのビジネス実用シーンでは、それら巨大モデルをそのまま使うのではなく、それを元に作られた特定のタスクに強い「専門家モデル」を、MoEなどの技術で効率的に組み合わせて使う形が主流になると予測されています。
更新履歴
- テンプレ4.1適用、内容をアップデート、FQC等複数の情報追加
- 初版公開
主な参考サイト
- DeepSeek-V2 Model Card – Hugging Face
- Evolving Transformers with Transformers – Sakana AI Official Blog
合わせて読みたい
- たとえ話でスッキリ理解!DeepSeekの全貌を解説
- sakana.ai: 日本発の革新的AI技術が世界を変える
- NVIDIAの独占は続くのか?AIチップの未来を徹底解説
- 直感で読むSakana AIのTransformer²解体新書
以上