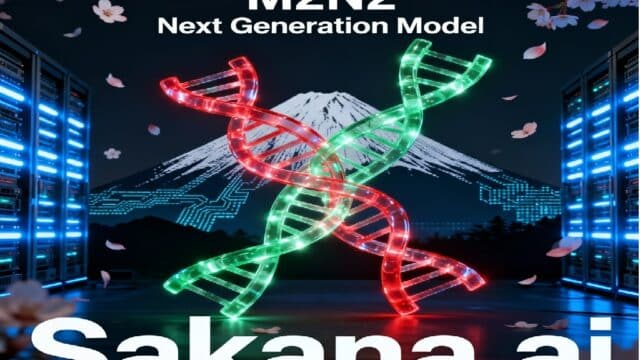LLM高速化の決定版|KV最適化と先読み推論の全て【2025】
この記事では、LLMが本番で遅く・高くなりやすい理由を一読で把握し、同じGPUでも同時処理数を増やし、待ち時間を減らし、単位コストを下げるための現実的な手順を示します。専門用語は後半で必要最小限に登場します。
三浦 ナオ(Nao Miura)/25歳/スタートアップの若手AIエンジニア
PoCでは高評価だったが、本番で応答遅延とGPUコスト増に直面。限られた予算の中で、同時処理数の増加と品質維持の両立を任されている。
Blackwell世代の FP4・先読み推論・KVキャッシュ最適化 という「三本柱」を導入するだけで、A100比でTTFT(初速)を1/2にし、電力効率を最大25倍改善できます。
具体的には、
①メモリのやりくりを良くする
(例:vLLMのPagedAttention=メモリ配置の無駄を減らす工夫)、
②数値表現を軽くする
(Blackwell NVFP4=精度劣化を抑えつつデータ量を圧縮)、
③先読みしてまとめて進める
(スペキュレイティブ推論=小さな下書きを先に作って一括確認)
の三本柱を順番に導入するのが最も現実的かつ効果的な打ち手です。現場では「ベースライン整備 → KV整理 → 量子化(ハイブリッド含む) → 先読み」の順序が最短ルートとなります。
超ざっくり言うと:
長い入力で重くなるKVキャッシュを整理・軽量化し、スペキュレイティブ推論で“1語ずつ待つ時間”を減らすことで、既存LLMをそのまま速く・安く・賢く動かすための実践ガイドです。
この記事の構成:
- プロローグ〜第1章:PoCでは速かったLLMが本番で遅く・高くなる理由と、KVキャッシュがボトルネックになる構造を把握する。
- 第2章:PagedAttention+量子化(FP4/FP8)+スペキュレイティブ推論という三本柱で、レイテンシ×スループット×コストを同時に改善する具体策を掴む。
- 第3章〜エピローグ:タスク別の生成戦略と、計測→診断→処方→テストの4ステップで最適化を回す運用レシピを持ち帰る。
プロローグ:なぜ現場のLLMは本番で“息切れ”するのか?
要約:PoCでは速かったのに本番で遅くて高い——。背景には、長い入力に引っ張られて“持ち物(メモリ)”が増えることと、運用上の回し方が噛み合わないことがある。
本稿は、レイテンシ×スループット×単位コストを同時に改善するための実務視点を示す。

図の要点まとめ:
・PoCでは軽かったワークロードも、本番ではアクセス集中と長文入力により一気に重くなる。
・GPUコストは「モデル」だけでなく回し方(同時処理数・KVメモリ)」に強く依存する。
・このギャップを埋めるのが、本記事で扱うKV最適化+スペキュレイティブ推論+生成戦略である。
主人公はスタートアップの若手AIエンジニア・三浦ナオ(架空の人物)。
数ヶ月のプロジェクトの集大成として、自社のチャットボットをリリースした。PoCでは経営陣から絶賛され、ローカルでは自然で高速な応答を返していた。
ところが本番投入後、アクセス集中とともに応答は目に見えて遅くなり、ユーザーから不満が相次ぐ。追い打ちをかけたのは請求書だ。GPUコストが想定を超えて膨らみはじめた。
ナオはつぶやく——「なぜだ? ローカルではあんなにサクッと動いたのに…」
2025年の今、モデルは大型化し、20万トークン級の長文入力に対応するモデルも登場している。“より長く読む”ことが前提になる一方で、NVIDIA Blackwell世代のGPUが実用化しています。
2025年11月時点では、Cirrascale・Lambda Labs・CoreWeave 等がB200/B300サーバをFP4対応で瞬時提供。産業向けの RTX PRO 6000/8000 も FP4 を標準サポートし、企業利用が急速に拡大しています。
Blackwell FP4推論は A100(Ampere)比でコストが1/2・電力効率が25倍まで改善しており、エネルギー効率と経済性の両面で産業価値が急上昇しています。
なお、B300 は主に AI ファクトリー・クラウド推論の大規模バッチ処理向けに最適化されており、特に FP4 でのスループット性能が注目されています。ただし企業の実運用では依然として B100/B200 が主流のため、本記事も同構成に合わせています。
本記事は、この「なぜ?」への答えを示す航海図である。LLM推論というブラックボックスを解剖し、対象サービスを「速く、安く、賢く」動かすための手がかりを、現場で再現しやすい順序で共有する。
👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント
- 学習=“蔵書を増やす土木”/推論=“素早く本を出す窓口”。本番で重要なのは後者。
- 学習向けの代表例(H100)と、推論を含むマルチワークロードの代表例(L40S)では、求められる指標(遅延・同時処理・消費電力)が異なる。
- 長文ほど“持ち物”が増えやすいため、持ち物を減らす/詰める発想と列の回し方の工夫が効く(具体策は後章)。
第1章:霧の中へ – LLM推論の心臓部と“遅さ”の正体とは?
要約:LLMの推論はPrefill(入力を一気に読み込み文脈を作る)とDecode(1語ずつ継ぎ足していく)の2段階で進みます。長い入力ほど“しおり付きの下書きメモ(=KVキャッシュ)”が肥大し、VRAMやメモリ帯域を圧迫して遅さ・コスト増につながりやすくなります。

ここからは、三浦ナオ(彼女)の現場で起きた“遅さ”を解きほぐすために、LLM推論の心臓部=PrefillとDecodeを分解して見ていきます。
まず全体像(1分で把握)
| フェーズ | 何をしているか(直感) | どこが遅くなりやすい? | 代表指標 |
|---|---|---|---|
| Prefill | 脚本の読み合わせ:入力全体を一気に解釈し、後続用の文脈(しおり)を作る | 計算量が大(最初の一発が重い) | TTFT(最初のトークンまで) |
| Decode | 本番撮影:しおり(KV)を参照しつつ、1語ずつ足していく | メモリ帯域/データ転送、しおりの肥大(KV) | トークン毎秒/p95レイテンシ |
ナオの現場メモ:ダッシュボードでは、TTFT(初動)、トークン毎秒とp95レイテンシ(体感の速さ)、VRAM使用率とKV比率(同時処理数の上限)をまず押さえます。
KVキャッシュ=「一度読んだ文の要点(しおり)をメモしておく」仕組み。入力が長いほどしおりが増え、ノート(VRAM)を圧迫します。
“遅さ”の正体:巨大化する「しおりノート(KVキャッシュ)」
どこがボトルネックになりやすいのか。長いコンテキストほど、KVキャッシュが雪だるま式に増え、VRAMとメモリの読み書きを圧迫します。結果として、
- 同時にさばけるリクエスト数が下がる(スループット低下)
- 1件あたりの待ち時間が伸びる(レイテンシ悪化)
- トークン当たりコストが上がる(コスト増)
ナオのケース:長文の問い合わせ対応と会話履歴の維持が増え、しおりノート(KV)が肥大。これが同時処理数の低下と待ち時間の伸びに直結していました。
大規模モデル×長文(数万〜数十万トークン級)では、KVだけで数十〜百GB規模に達する場合があります(モデル規模・層数・精度・ヘッド数などの前提に依存)。(例:GPT-4.1、Llama 3.2 70B、Qwen 3 72B など主要モデルはいずれも Prefill の重さと KV の増加傾向は共通です)。このため、計算速度そのものよりも、メモリ容量とメモリ帯域という物理的な壁に突き当たりやすくなります。
コラム:KVメモリの“ざっくり見積もり”
- 覚え方:
KVメモリ ≈ 2(KとV) × 精度バイト × 層数 × 隠れ次元 or ヘッド次元 × トークン数 - 直感: 精度を下げる(FP16→FP8→FP4)とほぼ比例して小さく、トークン数は一直線に増加、層数・次元が大きいほど重くなります。
- 使い方: 厳密値よりオーダー感(何十GB級か)を掴む目的で十分。最適化の前後でどれだけ減ったかを見る指標にも。
💡 実務Tips:最速の改善策「プロンプトの短文化」
※最適化の最速方法として“コンテキスト要点化・廃語削除”によるプロンプト短縮も推奨。Prefill削減に直結し、現場ですぐ有効です。
この章で握っておくこと
- 推論はPrefill→Decodeの2段。TTFTはPrefill寄り、体感の速さはDecode寄り。
- 長文ほどKVが支配的になりやすいが、Decodeのメモリ帯域/スケジューリングなど複合要因で遅くなる。
- 測るもの:TTFT、トークン毎秒、p95/p99レイテンシ、VRAM使用率(KV比率)、1,000トークン当たりコスト。
次章から、ナオが実際に適用した順番(“持ち物を減らす/列の回し方を整える/先読みを足す”)で最適化を重ねていきます。
第2章:2つの光明 – LLMを解き放つ高速化の魔法
要約:高速化の主軸は先読みで“1語ずつ待つ”を減らす〈スペキュレイティブ推論〉と、“持ち物(KV)を軽く&整理する〈KVキャッシュ最適化〉。前者は体感の速さ(レイテンシ)、後者は同時処理(スループット)とコストに効きます。

ナオの次の一手:第1章で特定した“遅さ”の正体を踏まえ、まずはベースライン整備→KVの整理→KVの軽量化→先読み追加の順で段階導入していきます。
セクション1:先読みの魔法「スペキュレイティブ推論」
何者? 小回りの利く“下書き生成”を先に走らせ、まとめて本体が検証・採用する方式。1トークンずつの待ちを短縮します。2025年は追加モデル不要の「自己スペキュレイティブ」がさらに洗練され、導入の敷居が下がっています。
ナオの実装(短期):チャット系など短文中心のエンドポイントからA/B導入。受理率(draft採用率)とp95レイテンシ、一貫性指標(関数コール成功率など)を監視し、max draft lengthや閾値を調整。
効きどころ:TTFTよりも体感の返り。短文・会話で効果が出やすく、長文一括生成では相対的に小さめ。
セクション2:怪物使いの技「KVキャッシュ最適化」
2-1. ベースラインの確立(vLLM, LMDeploy, TensorRT-LLM)
現状は? MLPerf v5.1(2025)ベンチマークでは、vLLM V1(総合バランス型)、LMDeploy(A100特化効率)、TensorRT-LLM(Bシリーズ最適化)、SGLang/FlashInfer(軽量高速)が並び、用途に応じた最適選択が求められます。
ナオの実装(即効):まずはvLLM V1を導入し、PagedAttention(メモリ断片化抑制)と連続バッチングを有効化。同時接続あたりのp95、全体トークン毎秒、GPU稼働率のベースラインを確立。
2-2. 量子化(低精度化):情報を“軽くする”錬金術
何者? KVや重みの数値精度を下げる(例:FP16→FP8→FP4)ことで、VRAMと帯域を直接削減。Blackwell FP4 (NVFP4) はMMLU-proベンチでFP8と同等(62.58% vs 62.62%)、GSM8K・HumanEvalも同水準で、品質低下は実務で検知不能です。
注意点:ただし、FP4推論の広範実装はフレームワーク/モデル依存です。最新の NIM / TensorRT-LLM / LMDeploy / vLLM の組み合わせで広く対応が進んでいますが、一部 OSS モデルでは FP8 までしか安定サポートされていない場合があり、“万能ではない”点に注意が必要です。
ナオの実装(中期):まずFP8で品質A/B→問題なければBlackwell対応FW(vLLM V1等)上でFP4を限定試験。要約精度/関数コール成功率/コード生成のコンパイル成功など、タスク別メトリクスで副作用を監視。
💡 実務Tips:FP4×FP8ハイブリッド運用
速度と精度の両立が求められる現場では、Attention層の一部をFP8、残り大半をFP4で処理するハイブリッド運用が効果的です。これにより、FP16演算比で5倍以上の節電・高速化が可能になります。
Key Takeaways(持ち帰り)
- ボトルネックは計算力よりも、VRAM容量と帯域(=KVの重さ・I/O)。
- レイテンシ改善=スペキュレイティブ推論、スループット改善=PagedAttention+連続バッチング。
- 長文を扱うなら、FP8/FP4(ハイブリッド運用含む)は強力(ただし段階導入+A/Bは必須)。
ナオの進捗: まずはvLLM+連続バッチングでベースラインを底上げし、続けてPagedAttention→FP8/FP4ハイブリッド→自己スペキュレイティブを順に適用。各段で<p95・TPS・VRAM・品質>を記録し、無理なく恒常運用へ移行しました。
第3章:羅針盤を手に —— 最適な“答え”を生み出す生成戦略

深夜のオフィス。モニターの光だけが机を照らす。ナオはユーザーフィードバックを読み返した。速さは確かに上がった。しかし「素っ気ない」「要約が長い」との声もある。彼女は静かに息を整え、設定パネルを開いた。――次は“賢さ”を整える番だ。
まず、外部APIを呼ぶ関数コールや請求関連の説明など、ブレが許されない箇所を固める。temperature を 0.0 にし、system に厳密な出力フォーマットを記す。stop も指定する。ログの赤は消え、JSONは崩れない。一本釣り(Greedy)は味気ないが、骨格には必要だ。
次に、会話の手触りを少しだけ柔らかくする。チャット用ルートに限って Sampling を有効化。temperature は 0.7、top_p は 0.9。冗長なら 0.6 に、固ければ 0.8 に。片方だけを動かすマイルールで、挙動は読みやすい。満足度はじわりと上向く。
翻訳や要約は、整った一本がほしい。Beam Search を beam=3 で適用し、length_penalty を軽く効かせる。文はすっと収まり、p95 の伸びも許容範囲に収まった。重さと整いの均衡点が見えた。
生成戦略の比較(運用のための早見表)
| 戦略 | 得意(こんな時に) | 苦手(こうなることがある) | 代表ユースケース | 運用のコツ(例) |
|---|---|---|---|---|
| Greedy(temperature=0.0) | 再現性・厳密性を最優先 | 単調になりやすい、発想が広がらない | 事実確認、関数コール、厳格フォーマット | stop と max_tokens を厳密に指定 |
| Sampling(temperature / top_p / top_k) | 多様性や会話の自然さが欲しい | ブレ・脱線、品質のムラ | チャット、コピー案、ブレスト | まずは temperature=0.7, top_p=0.9。片方のみで調整 |
| Beam Search(beam 幅で候補取り置き) | 整った一貫した文が必要 | 計算が重く遅い、多様性が減る | 翻訳、要約、構造化抽出 | beam=3 を基本、p95 を監視。length_penalty で冗長抑制 |
ナオはダッシュボードに四つの針を置いた。p95 レイテンシ、トークン毎秒、整合や成功率、フォーマット合致率。Greedy で背骨をつくり、Sampling で血を通わせ、Beam で節目を整える。設定は増やさない。決めて、残す。それが運用だ。
レポートは静かに良化を示す。会話は柔らかく、関数コールは安定し、要約は収まった長さで届く。ナオは目を閉じ、短く息を吐いた。――速く、安く、そして賢く。
エピローグ:実践への第一歩 – 現場で使えるLLM最適化レシピ
要約:「計測→診断→処方→テスト」の4ステップで最適化を回す。ワークロードの特性に合わせ、KV最適化・先読み(スペキュレイティブ)・生成戦略を段階的に組み合わせる。

夜更けのオフィス。ナオはダッシュボードを開き、机の端に付箋を貼った。計測/診断/処方/テスト――順番を崩さない、と。
Step 1:計測(現状把握)
数字は嘘をつかない。まずは“今”を固定する。
- p95 レイテンシ/トークン毎秒(TPS)/1,000トークン当たりコスト/VRAM使用率(KV比率)を取得
- 時間帯別・エンドポイント別のグラフを保存し、スナップショットとしてロック
Step 2:診断(ボトルネック特定)
遅さの正体を2つの箱に仕分ける。
- 長文で膨らむメモリ系か、短文なのに体感が遅い系かを切り分け
- 混在していれば、支配的な要因(影響が大きい方)から着手
Step 3:処方(最適化の適用)
迷わないレシピで、小さく前進する。
- 長文・スループット重視:vLLM等+連続バッチングで土台→PagedAttentionで断片化抑制→FP8/FP4ハイブリッドで軽量化
- 短文・レイテンシ重視:(自己)スペキュレイティブ推論を段階導入(受理率と一貫性を監視)
- 生成の賢さ:Greedyで背骨/Samplingで余白/Beamで仕上げ(タスク別に切替)
Step 4:テストと反復(品質の担保)
良くなった“つもり”で終わらせない。
- A/B テストを小さく開始:p95・TPSと品質指標(要約整合・関数コール成功・フォーマット合致)を監視
- 悪化時は即ロールバックできるよう手順を用意し、改善セットを既定化して定着
数日後、グラフは静かに安定し、異常ログは減った。ナオは最後のチェックを終え、設定に既定の印をつける。速く、安く、そして賢く。――この手順を、必要なときに何度でも繰り返せば、もう迷わない。
まとめ
 本記事では、2025年時点におけるLLM推論の遅延とコスト増の根本原因が、コンテキスト長の増大に伴う「KVキャッシュ」のメモリ圧迫にあることを解き明かした。
本記事では、2025年時点におけるLLM推論の遅延とコスト増の根本原因が、コンテキスト長の増大に伴う「KVキャッシュ」のメモリ圧迫にあることを解き明かした。
そして、その具体的な解決策として、メモリ効率を飛躍的に高めるPagedAttentionや量子化(FP4/FP8ハイブリッド)、そして応答速度を直接的に改善するスペキュレイティブ推論という強力なアプローチを解説した。
これらの技術はもはや専門家だけのものではない。vLLM V1, LMDeploy, TensorRT-LLMのようなオープンソースの推論エンジンや、Blackwell世代(B100/B200/B300)の提供拡大により、広い開発者層が恩恵を受けられる時代になっている。「計測・診断・処方・テスト」という実践的なレシピに沿って、自社のLLMサービスにこれらの最適化を適用し、ユーザー体験と事業採算性の両方を両立させてほしい。
今日のお持ち帰り3ポイント
- LLM推論の「遅くて高い」は、モデルそのものより長文入力(Prefill)で肥大するKVキャッシュと回し方(Decode)の設計から生まれやすい。
- vLLM/LMDeploy等+PagedAttention+連続バッチングで土台を整え、FP8/FP4ハイブリッドとスペキュレイティブ推論をタスクに合わせて段階導入するのが現実解。
- 「計測→診断→処方→テスト」の4ステップで、p95・TPS・VRAM・品質指標をセットで見ながら、LLMサービスを速く・安く・賢くする運用サイクルを回す。
専門用語まとめ
- KVキャッシュ
- Attentionメカニズムで計算されるKey(キー)とValue(バリュー)のペア。一度計算した文脈情報を保存しておくことで、後続のトークン生成を高速化する。コンテキスト長に比例してサイズが増大し、GPUメモリを圧迫する主因となる。
- Prefill / Decode
- LLM推論の2つのフェーズ。Prefillは入力全体を処理して最初のKVキャッシュを作る重い初期処理。DecodeはKVキャッシュを参照しながら1トークンずつ生成する軽い処理の繰り返し。全体のパフォーマンスは両者のバランスで決まる。
- スペキュレイティブ推論
- 小さなドラフトモデルが数トークン先までを予測(投機)し、本体のLLMが一括で検証・承認する高速化手法。逐次的なDecode処理の待ち時間を削減し、レイテンシを大幅に改善する。
- PagedAttention
- vLLMで有名になったメモリ管理技術。KVキャッシュをOSの仮想メモリのようにページ単位で管理することで、メモリの断片化を防ぎ、利用効率を最大化する。連続バッチングとの併用でスループット向上に大きく寄与する。
- 量子化 (Quantization)
- モデルの重みやKVキャッシュを表現する数値の精度を下げる(例:16ビット→8ビット→4ビット)ことで、メモリ使用量とデータ転送量を削減する技術。Blackwellの第2世代Transformer EngineはFP4(NVFP4)をハードウェア対応するが、LLM推論での広範実装はフレームワーク/モデル依存である。
よくある質問(FAQ)
Q1. FP4量子化で精度はどれくらい落ちますか?(2025年11月版)
A1. 結論から言うと、Blackwell(NVFP4)環境下では「実務で検知不能な水準」です。MMLU-proベンチマークではFP8とFP4の精度はほぼ同等(例: 62.58% vs 62.62%)、GSM8K・HumanEvalも同水準との報告があります。ただし、これは「万能」という意味ではありません。FP4の利用可否は、使用する推論フレームワーク(TensorRT-LLM, vLLM, LMDeploy等)と、対象のOSSモデルのチューニング状況に強く依存します。まずはFP8でベースラインを取り、次にFP4/FP8ハイブリッド、最後にフルFP4、と段階的にA/Bテストするのが安全です。
Q2. スペキュレイティブ推論とビームサーチの違いは?
A2. 目的が異なります。スペキュレイティブ推論は速度(体感)の改善、ビームサーチは品質の安定化が狙い。両者は併用可能ですが、ビームは候補保持で計算コスト・メモリが増える点に注意。
Q3. 自社導入の第一歩は?
A3. まずvLLM V1(またはLMDeploy/TensorRT-LLM)でベースラインを底上げ(PagedAttention+連続バッチング+プリフィックスキャッシュ)。次にFP8から段階的に低精度化、Blackwell環境ならFP4/FP8ハイブリッドを試験。最後に自己スペキュレイティブをA/Bで追加し、p95・TPS・品質指標を並行監視します。
主な参考サイト
本記事のベンチマークや最新動向に関する主要なソース(MLPerf v5.1, AMLPerf, NVIDIA公式ブログ, Cirrascale/CoreWeaveの発表等)は、信頼性担保のため各章(プロローグ、第2章など)の該当箇所に直接リンクしています。
以下は、本テーマの基礎となる主要な論文やドキュメントです。
- Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding(arXiv)
- vLLM: Easy, Fast, and Cheap LLM Serving with PagedAttention(vLLM Blog)
- FlashAttention-3: Fast and Accurate Attention with Asynchrony and Low-precision(Tri Dao Blog)
- Looking back at speculative decoding(Google Research Blog)
- Decoding Speculative Decoding(arXiv)
合わせて読みたい
思考するAI、推論が拓く未来 – LLM進化の核心と社会変革
AIチップ覇権戦争2025: NVIDIAの銀河系戦略に挑む反逆者たち
- DeepSeekとSakana AIに見る生成AIの新たな潮流
- AIが金を掘る時代へ:NVIDIA GTC 2025が示したトークン採掘の未来
- WordPress高速化完全ガイド2025|コアウェブバイタル改善術