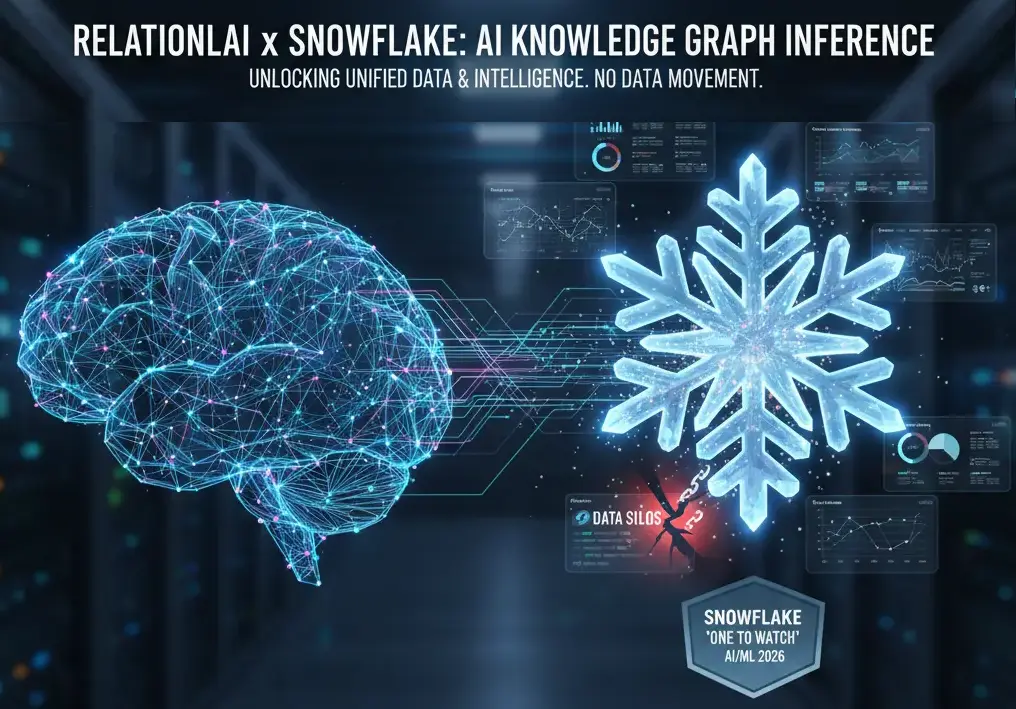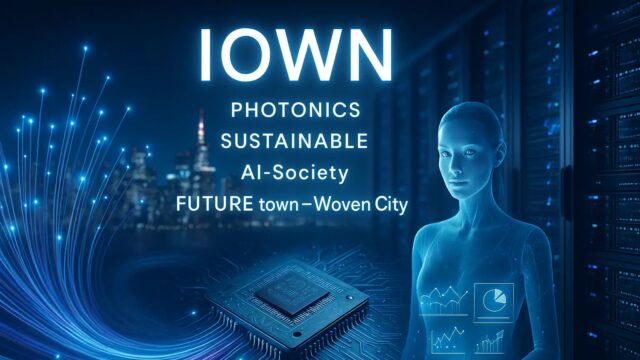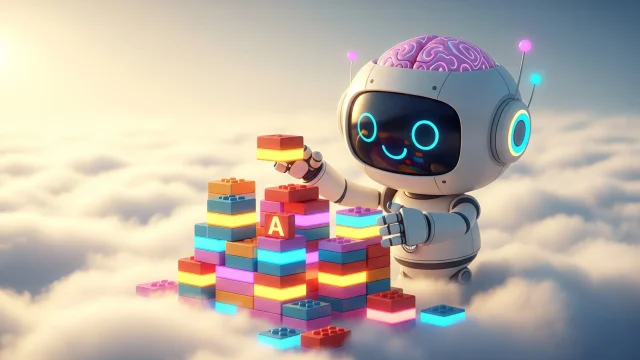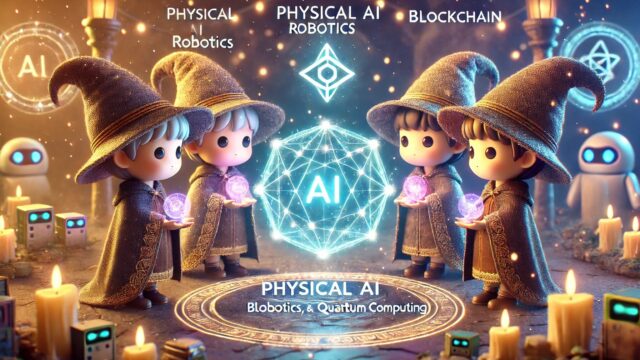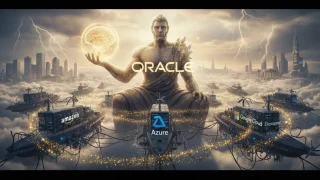RelationalAI×Snowflake:最新ナレッジグラフ推論解説【2025】
【2025/9/30 最新】RelationalAIが Snowflake社主催の「Modern Marketing Data Stack 2026」で AI/ML 分野の “One to Watch” に選出。
本記事では、サイロ化と用語不一致をリレーショナル知識グラフ(RKGS)で解消し、Snowflake上でデータ移動なしに推論・最適化まで一気通貫で回す方法を解説します。さらに、90日導入ステップと運用の勘所を、実務担当者向けに整理しました。
- 要点1:部門ごとにバラつく用語・定義を、データのそばのセマンティクスで統一し、ダッシュボード不一致を解消。
- 要点2:返品・遡及修正へ差分再計算(IVM:Incremental View Maintenance)で準リアルタイム追随、速報性とコストを両立。
- 要点3:目的関数×制約で意思決定を数学化し、在庫・需給・審査・マーケに説明可能な最善案を提供。
はじめに:企業が直面する「データ活用の壁」
要約:データは集まったのに定義がバラバラ──壁の正体は意味の断絶と偶発的な複雑性です。
検証ポイント:「顧客」定義のズレ/部門別ダッシュボード不一致/仕様変更のたびに増えるコードと会議時間
 営業の「アクティブ顧客」と企画の「エンゲージドユーザー」は同じでしょうか?
営業の「アクティブ顧客」と企画の「エンゲージドユーザー」は同じでしょうか?
意味の不統一こそ、AI/BIの全社活用を阻む最大の障害です。
さらに、要件→コードへの翻訳で意図が歪み、偶発的複雑性が雪だるま式に拡大します。
結果、手作業の調整とシステムのサイロ化が進み、コスト増・エラー増・意思決定の遅延が常態化します。
本記事では、この“壁”をSnowflakeの境界内で崩す新機軸――RelationalAI(RKGS+IVM+処方的最適化)のアプローチを解説します。
RelationalAIとは:データを動かさず「意味と推論」を載せる
RelationalAIは、Snowflakeに“隣接”して動くナレッジグラフ+推論の補助実行エンジン(ソフトウェア)。
既存データを移動せず、同一アカウント境界のまま「関係(リレーション)・ルール・予測・最適化」を一体運用できます。
Snowflakeとのネイティブ統合が強みですが、製品自体はマルチクラウド展開です。
先に誤解を解く(2点)
- Snowflake専用ではない:統合が強力なだけで、製品自体はマルチクラウド展開。
- 「コプロセッサ」はハードではない:本記事でのコプロセッサは比喩。Snowflakeの汎用処理の“隣で”知識と推論を担うソフトウェア層(補助実行エンジン)を指す。
何が違う? 一般的なグラフDBとの違い
多くのグラフDBは「ノードと矢印」でつながりを表し、関係は“線”として扱います。
これに対してRKGS(RelationalAI)は、関係そのものを独立したデータ(レコード)として管理し、日時・価格・チャネルなどの属性や、ルール/制約/履歴を同じ土台で扱います。
その結果、定義の一元化・差分再計算(IVM)・制約下の最適化まで、データを動かさず同一基盤で完結します。
| 観点 | 一般的なグラフDB | RKGS(RelationalAI) |
|---|---|---|
| 関係の表現 | ノード間の矢印(エッジ)が中心。関係は「線」として保持 | 関係を“データ行”として扱う(主語・述語・目的語+属性・制約・履歴を一体管理) |
| 事実と意味 | 事実グラフ中心。導出や定義はアプリ側に散在しがち | 事実(ベース)と導出(定義・ルール)を同一基盤で一元管理 |
| 推論の範囲 | 経路探索・パターン照合が主用途 | 再帰・制約・最適化まで一枚岩。処方的に「最善案」を返せる |
| 更新への強さ | 全再計算になりやすく運用負荷が増大 | 差分再計算(IVM)で準リアルタイム追随。返品・遡及に強い |
| 実行位置 | 専用基盤に別置き→データ移動が前提になりやすい | Snowflake境界内で“隣接実行”→データを動かさない |
最短の理解:意味をデータのそばに置き、差分で回し、制約の中で最善案を返す。しかもSnowflakeの境界内で完結——それがRelationalAI。
「意味の断絶」を解く:RKGSで事実と定義を一箇所に
朝の合同会議は続く。
営業は「アクティブ顧客が2,300」、企画は「エンゲージドユーザーは1,850」。
数字が合わない理由は、“事実”は同じでも“数え方(定義)”が部門ごとに違うからです。RKGSは、この定義の違いを同じ土台で管理し、ダッシュボードの不一致を根本からなくします。→-導出関係(Meaning).jpg)
アクティブ顧客やエンゲージドといった用語を、社内で同じ意味にそろえます。
「ATP(Available to Promise)=在庫 − 予約数」のような計算式も、一か所で決めて共有します。定義を変えたときは、すべてのダッシュボードにすぐ反映されます。
RKGS(Relational Knowledge Graph System)は、Snowflake上の「購入・在庫・予約・支払い」といった事実データと、「アクティブ顧客」「ATP」などの数え方・ルール(定義)を同じ場所で管理します。
つまり、「何が起きたか(事実)」と「どう数えるか(定義)」をセットで持ち、常に同じ答えを返せるようにする仕組みです。
- 在庫表示の食い違い:
ECでは「在庫あり」なのに、出荷側は「出せない」。予約分が在庫から引かれていないのが原因。 - RKGSの解き方:
ATP=実在庫 − 予約数 を公式として一か所に定義。すべての画面と部門が、同じ公式から同じ数値を取るようにする。 - 運用の軽さ:
期間や閾値を変えるときは、定義だけ更新すれば全体に即反映。個別システムの修正や全件再集計は不要。
その結果、部門間のダッシュボードは一致し、会議は「数字合わせ」から“どの施策を打つか”の議論に進みます。
グラフDBとの違い:関係を「線」ではなく“入れ物”に
一般的なグラフDBは関係を「線(エッジ)」で表しますが、RKGSは関係そのものを情報を入れる“入れ物(テーブル行)”として扱います。
だから、なぜその結論になったかの説明や、社内ルールの適用、在庫配分などの最適化まで同じ場所で回せます。
会議で「昨日の売上、どの施策が効いた?」と部長。営業は「Aキャンペーンです」と答える一方、企画は「地域プロモの影響も大」と主張。
一般的なグラフDBだと「顧客A → 製品B(購入)」という“線”は引けますが、その線にいつ・どこで・いくらで・どのキャンペーンでといった詳しい事情を書き込みにくい。
RKGSなら、この関係そのものが正式な入れ物なので、日時・店舗・価格・キャンペーンIDなどを一緒に持てます。すると、「なぜAキャンペーンと言えるのか」を根拠つきで示せるわけです。
違いの核心(ポイントだけ)
- 関係=入れ物:ノード間の“線”ではなく、関係自体が属性を持つ正式レコード。
- 理由が残る:関係に紐づく属性(日時・場所・施策・契約など)から、結論の根拠をたどれる。
- ルールと制約を直結:会計・法務の条件や社内ポリシーを、定義として同じ基盤に置ける。
- 最適化まで一体:在庫・需給・審査ラインなどを目的関数×制約で解き、現場に“最善案”を返せる。
- 差分更新(IVM)で速い:返品や遡及修正が来ても、変わったところだけ再計算。速報性とコストの両立。
まとめると、RKGSは「矢印の集まり」ではなく“関係そのものを第一級で扱う”知識の土台です。定義の統一から理由説明、そして最適化による打ち手の提示までを、Snowflakeの境界内で一気通貫に運用できます。
偶発的な複雑性を減らす:REL言語と差分再計算(IVM)
昨日の合同会議。部長が「昨日の売上、どの施策が効いた?」と尋ねると、営業は「Aキャンペーンです」と即答し、企画は「地域プロモの寄与が大きい」と反論した。両者が見ているダッシュボードの数字が微妙に違うせいで、議論は空回りする。原因は単純で、定義と集計のルールが部門ごとにばらけているからだ。
RelationalAI は、この“意味のずれ”を最初から潰しにかかる。
やり方は二つの柱で説明できる。
一つ目の柱は「REL(関係のための宣言言語)」
やりたいことを短く書く。
例えば「アクティブ顧客=過去14日以内に購入した人、または連続ログイン中の人」「昨日の売上=日付が昨日の確定取引の合計」といった定義を、手順ではなく定義そのもので表す。定義は共有の置き場にあり、営業も企画も同じ文を参照する。期間窓や閾値を変えても、定義の差し替えだけで全員に同時反映される。
二つ目の柱は「IVM(差分再計算)」。
数字が変わったところだけを更新する仕組みだ。
返品が1件あった、キャンペーン対象を数%広げた――そんな変更が起きても、全件やり直さずに影響範囲だけが再計算される。だから、朝の売上速報は止まらないし、会議中に定義を微修正しても数分で更新が届く。
この二つがそろうと、同じ出来事を同じ言葉で数え、変更は即座に全員に届く。
営業の画面も企画の画面も、元になっている定義は一つだけ。
部長が「では、Aキャンペーンと地域プロモの寄与を分解して見せて」と言えば、REL に書かれたルールに沿って、IVM が差分を保ったまま寄与分解を再計算する。議論は「数字合わせ」から「打ち手の検討」に戻る。
要するに、RelationalAI はデータそのものを動かさず、定義(意味)をデータのそばに置いて共有し、変化点だけを素早く更新する。これだけで、部門間の食い違いは日常から例外に変わる。今後の会議では、誰がどの画面を見ていても同じ答えになる――その状態が“標準”になる。
4つの推論を同じ土台で回す:グラフ/ルール/予測/最適化
ひとつの知識基盤の上で「見つける → 確かめる → 見通す → 決める」を往復できます。
ツールを行き来せず、同じデータ・同じ定義のまま結論まで到達するため、話が早く、根拠も残ります。
営業と企画のつづき:寄与は何が効いた?
部長「昨日の売上、Aキャンペーンと地域プロモのどっちが効いた?」。
チームはRKGSの上で、次の4ステップを同じ土台のまま回します。
1)グラフ(関係を見つける)
何が何に影響したかのつながりを抽出します。たとえば
「キャンペーン閲覧 → カート投入 → 決済」の経路や、
共購買ネットワーク、地域コミュニティの塊(クラスター)を見つけます。
入力:クリック・購買履歴・位置情報
出力:影響経路・中心ノード・コミュニティ
2)ルール(根拠で確かめる)
「直前24時間に接触した施策のみを寄与対象」や
「社内購入は除外」など、寄与の判断基準をルールで明示。
その場の思いつきではなく、誰が読んでも同じ判定になります。
入力:寄与ルール・除外条件・コンプラ規定
出力:施策ごとの寄与フラグと根拠ログ
3)予測(先行きを見通す)
関係の特徴(つながりの強さ・近さ・所属クラスター)を使って、
「次に買いそう」「離脱しそう」「需要が跳ねそう」を見積もります。
ルールで定義した用語や制約をそのまま特徴量にできるので、説明がしやすいのが利点です。
入力:関係特徴・過去の反応・季節要因
出力:来週の需要予測・離脱確率・見込み反応
4)最適化(制約の中で決める)
目標(売上・利益・在庫回転)と制約(在庫・納期・法務・予算)をセットにして、
「どこに予算を配分し、何をいつ補充するか」の
最善案を返します。
根拠(使われたルール・在庫・制約違反の回避理由)も同時に残ります。
入力:目的関数・制約・最新在庫と予約
出力:配分案・補充案・期待効果と説明
ポイント:
- 同じ定義・同じデータで4つのステップを往復できる(途中でツールや定義を変えない)
- 寄与の計算式や除外条件はルールとして可視化され、あとから監査・再現が容易
- 差分再計算(IVM)で、返品1件・閾値変更などの小さな変化にもすぐ追随
まとめ:「見つける→確かめる→見通す→決める」を同じ土台で回せるから、
会議は数字合わせから打ち手の検討へ。現場が動きやすい理由と根拠が、最初から最後まで揃います。
4つの推論を同じ土台で回す:グラフ推論/ルールベース推論/予測分析/最適化分析

要約:
ひとつの知識基盤の上で「見つける → 確かめる → 見通す → 決める」を往復できます。ツールを行き来せず、同じデータ・同じ定義のまま結論まで到達するため、話が早く、根拠も残ります。
グラフ推論(関係を見つける)
施策と購買のつながりを抽出。例:「キャンペーン閲覧 → カート投入 → 決済」の経路、共購買ネットワーク、地域コミュニティの塊。
入力:クリックや購買の履歴データ/出力:影響経路・中心ノード・コミュニティ
ルールベース推論(根拠で確かめる)
寄与の判定基準を明示。例:「直前24時間に接触した施策のみ寄与対象」「社内購入は除外」。誰が見ても同じ判定になり、監査も容易。
入力:寄与ルール・除外条件・コンプライアンス規定/出力:施策別の寄与フラグと根拠ログ
予測分析(先行きを見通す)
つながりの強さや近さ、所属クラスターなどの関係特徴から、「次に買いそう」「離脱しそう」「需要が跳ねそう」を見積もる。定義や制約を特徴量として使えるので説明しやすい。
入力:関係特徴・過去反応・季節要因/出力:需要予測・離脱確率・見込み反応
最適化分析(制約の中で決める)
目標(売上・利益・在庫回転)と制約(在庫・納期・法務・予算)をセットにして、「どこに予算を配分し、何をいつ補充するか」の最善案を返す。使われたルールや在庫、制約回避の理由を同時に保存。
入力:目的関数・制約・最新在庫と予約/出力:配分案・補充案・期待効果と説明
ポイント:
- 同じ定義・同じデータで4つの推論を往復(途中でツールや定義を変えない)
- 寄与の計算式や除外条件はルールとして可視化され、あとから監査・再現が容易
- 差分再計算(IVM)により、返品や閾値変更など小さな変化にもすぐ追随
まとめ:見つける → 確かめる → 見通す → 決めるを同じ土台で回せるから、会議は数字合わせから打ち手の検討へ。現場が動きやすい理由と根拠が、最初から最後まで揃います。
最新アップデート:Text-to-Reasonerとエコシステム
【2025年9月30日】Snowflakeの「Modern Marketing Data Stack 2026」でRelationalAIがAI/ML Development & DeploymentカテゴリーのOne to Watchに認定。マーケ領域では、関係性を用いたハイパーパーソナライゼーションや予測セグメンテーションの実装文脈で評価が高まっています。
【2025年6月3日】Snowflake SummitでText-to-Reasoner(プレビュー)を発表。RAGやtext-to-SQLの一歩先として、RKGSに定義された意味・ルール・制約に基づく推論/シミュレーションを志向。AT&Tとの共同提出でSpider 2.0ベンチマークにて上位成績を発表。
【2025年9月23日】Snowflake・Salesforce・BlackRock・dbt Labs・RelationalAIなどがOSI(Open Semantic Interchange)を共同発表。メトリクス・ディメンション・関係の共通語彙をオープンに定義し、ベンダー間の意味互換性を高める“セマンティクスのロゼッタストーン”構想が動き出しました。
実世界の片鱗:説明可能な推奨と大企業導入例
部長が「この製品、なぜ今補充なの?」と聞くと、画面には“理由”が並びます。
・安全在庫を下回っている(目安は7日分)
・リードタイムは14日、予約注文が120件ある
・代替品の在庫も薄い/販促Aが継続中
結論と根拠がセットで見えるので、議論は「数字合わせ」ではなく「次の一手」に集中できます。
公開されている導入例(要点)
・AT&T:
Snowflakeの公式発表で、RelationalAIを使った不正検知や依存関係の可視化が紹介。
・Cash App(Block):
コミュニティ検出や中心性分析など、グラフ手法の活用事例が資料で説明。
・Blue Yonder:
サプライチェーンのナレッジグラフで、レガシーコードを大幅削減し、処理時間を短縮したと一次情報で言及。
現場でのメリット(まとめ)
・推奨に“なぜそう言えるか”が添えられ、納得と実行が進む
・ルールや制約、計算式が明示され、説明責任や監査に強い
・差分更新(IVM)で、返品や遡及修正にもすばやく追随
まずは自社の優先領域で「結果」と「理由」を同じ画面で出す体験を作る。そこから全社展開へ広げるのが近道です。
どのビジネスに向くか:在庫・需給・不正・売上認識・マーケ
要約:
定義が食い違い、かつ素早い判断が求められる領域ほど、RKGS+IVM+最適化の相性が良い。結果だけでなく「なぜその結果か」の理由も示せるため、現場が動きやすくなります。
よく効く場面の例
- 在庫/需給:在庫と予約が別管理で数字が合わない問題を、
RKGSで定義を一箇所に集約し、
IVMで入出荷や返品の差分だけ即時反映。
欠品率が下がり、納期の守りやすさが上がります。 - 不正検知:アラート過多で対応が追いつかない状況を、
ルールをRKGS側に明示し、IVMで新しいパターンだけ再計算。
偽陽性が減り、初動が速くなります。 - 売上認識:遡及修正のたびに全再集計していた運用を、
締め条件や返品の扱いなどの定義をRKGSに置き、
IVMで変更点だけ再計算。月次締めの時間を短縮できます。 - マーケティング:部門ごとにKPI定義が違い効果測定で揉める課題を、
用語と計算式を共通化し、寄与分解を差分で更新。
施策の良し悪しがすぐ見えるようになります。
導入すると何が変わるか
- 定義の一本化で「数字合わせの会議」が減る
- 差分再計算で速報が途切れず、意思決定が早まる
- 最適化で目的と制約を明文化し、現実的な最善案を自動提示できる
効果を測る指標の例
- 欠品率、納期遵守率
- 偽陽性率、初動までの時間
- 月次締め所要時間
- LTVや施策ROIの改善幅
まとめ
課題の根っこは「定義が散らばっている」「更新が遅い」「次の一手が決まらない」の三点です。
RKGSで定義をまとめ、
IVMで差分だけ素早く回し、
最適化で打ち手を決める。
この流れが入ると、KPIがぶれずに回り始めます。
まとめ:データを動かさず「意味と推論」を現場に届ける
RelationalAIは、Snowflakeのアカウント境界の中で、データのそばに意味(セマンティクス)を置き、差分だけを素早く更新し、決められた制約の中で最善案を返すための“根拠ある自動化”の土台です。
部門ごとの用語ズレやシステムのサイロ化、全件再計算の遅さといった長年の悩みを、RKGS+IVM+最適化の組み合わせで具体的に解消します。
まずは「1ドメイン × KPI固定」で90日間のスモールスタート。
その後は、OSIによる共通語彙や SPCS のネイティブ実行を活かして横展開し、欠品率、納期遵守、不正検知の偽陽性、月次締めの所要時間、LTV といった“経営に効くKPI”で定着させてください。
専門用語まとめ
- RKGS(Relational Knowledge Graph System:リレーショナル知識グラフ)
- 事実(ベース関係)と意味(導出関係)を同基盤で扱い、定義ズレの可視化と説明可能性を高めるアプローチ。
- IVM(Incremental View Maintenance:差分再計算)
- 変更の影響範囲だけを更新する方式。速報性・コスト・監査性を両立させる。
- SPCS(Snowpark Container Services)
- Snowflake内でコンテナ化アプリを実行する仕組み。RelationalAIのネイティブアプリがここで動作し、データ移動なしで推論を実行。
- GNF(Graph Normal Form:グラフ正規形)
- 第六正規形(6NF)に基づく完全正規化。各リレーションはキー列+最大1つの値列で、NULLや空行を排除。
- OSI(Open Semantic Interchange)
- Snowflake・Salesforce・BlackRock・dbt Labs・RelationalAIなどが推進する、メトリクス・ディメンション・関係の共通語彙を定めるオープン標準。
- Text-to-Reasoner
- 自然文の質問を、定義・ルール・制約に基づく推論に接続する機能。2025年時点ではプレビュー段階。
よくある質問(FAQ)
Q1. RelationalAIはSnowflake専用ですか?
A1. 専用ではありませんが、Snowflakeネイティブ統合(Marketplace導入/SPCS稼働)に強みがあり、境界内実行でデータ移動を不要化できます。
Q2. グラフDBと比べたメリットは?
A2. RKGSは関係を第一級で扱い、再帰・制約・最適化を同じ知識基盤で運用。導出の根拠追跡が容易で、監査・説明責任に強いのが特徴です。
Q3. どこから始めるのが最短ですか?
A3. 在庫・需給/不正/売上認識/マーケなど、KPIと痛みが直結する1ドメインで90日スコープ。定義統一→IVM→最適化の順で段階導入が現実的です。
Q4. 既存BIや業務OSは使い続けられますか?
A4. はい。推論結果はSnowflakeのビュー等で公開でき、既存のダッシュボードや業務OSがそのまま消費できます。
主な参考サイト
- RelationalAIが「Modern Marketing Data Stack 2026」でOne to Watchに認定(2025-09-30)
- Snowflake:Open Semantic Interchange(OSI)共同発表(2025-09-23)
- Snowflake公式ブログ:OSIの狙いと背景
- RelationalAI:Text-to-Reasonerほか新機能(Snowflake Summit 2025)
- Snowflake公式ブログ:AT&TにおけるRelationalAI活用の紹介
合わせて読みたい
- GraphRAGとは
- 【2025最新】Palantir AIPとオントロジー完全ガイド ─ Snowflake/Databricks連携と国内事例
- Databricks対Snowflake、AI時代のデータ基盤を比較
- LangGraph v1.0徹底解説:StateGraphでRAG構築【2025】
- 【2025年決定版】RAG精度を劇的に引き上げる8つの鍵
更新履歴
- 初版公開
(2025年9月30日のMarketing Stack認定、9月23日のOSI発表、6月3日のText-to-Reasoner発表等、2025年の最新情報を反映)